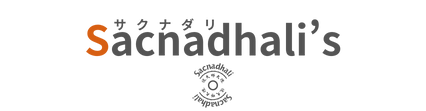神社への参拝は、日本の伝統文化として古くから大切にされてきました。正しい作法を知ることで、神々とのつながりを深めることができます。ここでは、一般的な神社の参拝方法とその所作の意味、特定の神社における独自の参拝方法について解説します。
一般的な神社の参拝方法
多くの神社では『二礼・二拍手・一例』、もしくは『二拝二拍手一拝』が基本とされています。これは神社本庁が推奨する参拝方法です。
①鳥居をくぐる前に一礼
神域に入る前に、鳥居の前で一礼します。鳥居をくぐる時や参道を歩く時は、なるべく端を歩きましょう。真ん中は神様が通る場所とされています。
②手水をとる:手水舎(ちょうずや)で身を清める
境内に入ったら、まず手水舎で手と口を清めます。
- 右手で柄杓を持ち、左手を洗う。
- 柄杓を左手に持ち替え、右手を洗う。
- 再び柄杓を右手に持ち替え、左手に水を受けて口をすすぐ。
- もう一度左手を洗い、最後に柄杓を立てて残った水で柄を清め、元の位置に戻す。
下の動画は神社本庁による正式な手水の作法の引用です。
③拝礼方法(二礼・二拍手・一礼)
神前に進んだら軽くお辞儀をし、お賽銭を入れ、鐘を鳴らします。
- 二礼(にれい):背筋を伸ばし、腰を30度~45度に折り、深くお辞儀を2回行います。
- 二拍手(にはくしゅ):両手を胸の高さで合わせ、右手の指先を少し下にずらします。肩幅程度に両手を開き、2回手を打ちます。
- 一礼(いちれい):再度、深くお辞儀を1回行います。
神様への感謝の気持ちや願い事は二拍手の後に伝えます。
この一連の所作は、神々への敬意と感謝の気持ちを表現しています。二拝・二拍手・一拝(にはい・にはくしゅ・いっぱい)とも言われますが、拝は腰を90度に折り、より深いお辞儀で敬意を表します。礼よりも拝の方が深いお辞儀と覚えておきましょう。
下の動画は神社本庁による正式な拝礼方法の引用です。
出雲大社の参拝方法
出雲大社では一般的な「二礼・二拍手・一礼」とは異なり、「二礼・四拍手・一礼」の作法が伝統とされています。古来より出雲大社独自の風習として受け継がれてきた参拝方法です。
四拍手には神々への特別な敬意と感謝の念が込められているとされています。
この四拍手の作法には、いくつかの由来があります。
1. 例祭の伝統から
出雲大社では、毎年5月14日に行われる最も重要な祭典である「例祭」において、神前で八拍手を打つ習わしがあります。
この八拍手には神々への敬意と感謝を無限に表す意味が込められており、日常の参拝ではその半分の四拍手が正式な作法となっています。
2. 四方への祈り
四拍手は、東西南北の四方を表すとも言われています。これは、天地四方の神々に敬意を表し、広く平安を祈るという意味が込められています。
3. 「四」の持つ縁起の良い意味
日本語において「四(し)」は「幸(しあわせ)」を連想させることから、四拍手には幸福や繁栄を願う意味もあると考えられています。
このような理由から、出雲大社では独自の作法として「二拝四拍手一拝」が受け継がれています。
吉水神社の参拝方法
奈良県吉野郡吉野町にある吉水神社は、特別な参拝作法を持つ神社として知られています。この神社では、二礼十七拍手一拝の作法が行われます。
これは祀られている別天津神(ことあまつかみ)の5柱と神代七代(かみよななよ)の12柱、合計17柱の神々に敬意を表すためのものです。
十七拍手は、4回ずつ4セット行い、最後に1回打つ、計17回の拍手となります。
吉水神社はもともと『吉水院』として約1300年前に役行者(えんのぎょうじゃ)によって創建され、修験道の僧坊として始まり、南北朝時代には南朝(後醍醐天皇)の皇居として使用され、明治初年の神仏分離令により、吉水神社と改称されました。
そのため後醍醐天皇と、南朝ゆかりの楠木正成公、吉水宗信法印公が御祭神として祀られています。
神社でのNG行動
神社は神聖な場所であり、参拝の際にも身を清めてから入る場所です。他の宗教で言う礼拝所に該当します。節度を持ってお参りしましょう。
不潔な服装での参拝
神社は神聖な場所です。一般の参拝の場合は正装でとは言いませんが、派手過ぎず、清潔な服装で参拝しましょう。
神域への立ち入り
境内には、神職の方以外(神職の方でも)立ち入りが許されない場所があります。立ち入り禁止の記載がある場所や、結界の中には絶対に立ち入らないようにしましょう。
境内のものを持ち帰る
これは境内の文化財や有価物に限ったことではありません。小石や砂のような自然物であっても持ち帰ってはいけません。理由は主に下の2点です。
1.境内にあるものは全て神様のものという考え方。
2.払った厄や参拝者の念などが籠っているという考え方。
境内で騒ぐ
観光目的もありますが、本来は身を清め、神様に感謝を伝える場です。静かに参拝しましょう。
願い事ばかりする
ついつい御利益にすがる気持ちは分かりますが、まずは常日頃から見守ってくださっている神様に感謝の気持ちを伝えましょう。
動物の持ち込み
四つ足の動物は縁起が悪い対象とされており、基本的に神社への動物の持ち込みは禁止です。特別に許可の出ている神社を除き、動物(ペット)は持ち込まないようにしましょう。
特にお稲荷さんの遣いは狐で、犬との相性が悪いです。
その他
神社に限らず、他の場所でも禁止されていること(落書きや放尿、器物損壊など)は言うまでもありません。礼拝所不敬罪という刑罰も存在しますので注意しましょう。
それからお賽銭についてですが、小さな小銭をじゃらじゃら入れることはNGではないのですが、両替をする際にも手数料がかかるということも頭に入れておきましょう。
まとめ
神社によっては独自の歴史や風習に基づいた参拝作法を持つ場合があります。
参拝する神社の作法について事前に確認し、その神社の伝統に従って参拝することは大切です。しかし最も重要なのは、神社を訪れ、穢れのない気持ちで神様に手を合わせ、日ごろの感謝を申し上げることです。
禁止事項だけは守りつつ、気軽に参拝してみてはいかがでしょうか?