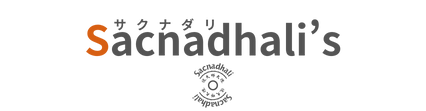月読神社の御由緒
月読神社(つきよみじんじゃ)は、487年(顕宗天皇3年)に壱岐から勧請され、山城国葛野郡(現在の西京区)に創建された式内名神大社。
856年に現在地へ遷座され、以降は松尾大社の境外摂社として「松尾七社」の一社として崇敬を集めてきました。
神功皇后(じんぐうこうごう)ゆかりの『月延石(つきのべいし)』を御奉祀しています。
月読神社の御祭神
- 月読尊(つきよみのみこと) – 有名でありながら、実は記紀にもほとんど登場しない月読尊。伊弉諾尊が黄泉の穢れを落とす禊ぎの際に生まれた三貴子(みはしらのうずのみこ)の一人で、天照大御神の弟。保食神(うけもちのかみ)を殺めたことで太陽を司る姉と喧嘩になり、交わることのない月の神となった。
月読神社の御利益
境内にある『月延石』には、神功皇后が石でお腹を撫でて元気な御子を授かったという伝承があり、古来より子授けと安産の信仰が根強いです。
また、縁結び、学業成就、海上安全、罪穢れ清めなどのご利益が境内の末社や御神水を通じて信仰され続けています。
月読神社の詳しい所在地
- 住所:〒615‑8296 京都府京都市西京区松室山添町15
- アクセス:阪急嵐山線「松尾大社駅」から徒歩約10分、市バス「松尾大社前」下車10分。
- 駐車場:境内に無料スペースがありますが台数は少ないです。松尾の大社の駐車場か、近隣のコインパーキングをご利用ください。
サクナダリの感想
鳥居をくぐり静かな参道を進むと、拝殿の奥に「月延石」がひっそりと祀られています。
千年を超える安産祈願の歴史と神功皇后の思いがそっと伝わってくるようでした。柔らかく満たされた感覚とともに、“命”のつながりを感じられる、そんな温かい時間がここには流れていました。
ギャラリー